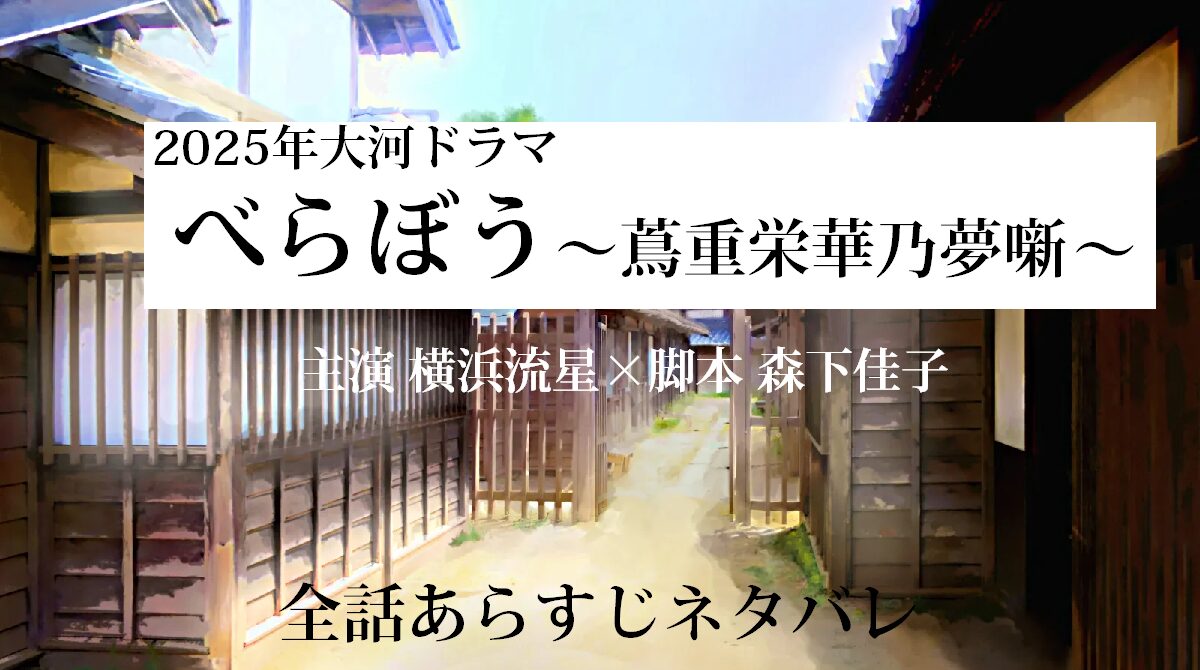大河ドラマ【べらぼう】のネタバレあらすじを最終回まで全話紹介!あらすじ概要、なぜ蔦屋重三郎はヒットメーカーになったのか、蔦屋重三郎とTUTAYAとの関係、蔦屋重三郎の年表、についてもお伝えします。
>最終回(48話)ネタバレはこちら
「べらぼう」の動画は【U-NEXT】NHKがオススメ。
- 【べらぼう】ネタバレあらすじを最終回まで!
- 第1話「ありがた山の寒がらす」
- 第2話「吉原細見『嗚呼御江戸』」
- 第3話「千客万来『一目千本』」
- 第4話「『雛形若菜』の甘い罠」
- 第5話「蔦に唐丸因果の蔓」
- 第6話「鱗剥がれた『節用集』」
- 第7話「好機到来『籬(まがき)の花』」
- 第8話「逆襲の『金々先生』」
- 第9話「玉菊燈籠(たまぎくどうろう)恋の地獄」
- 第10話「『青楼美人』の見る夢は」
- 第11話「富本、仁義の馬面」
- 第12話「俄なる『明月余情』」
- 第13話「幕府揺るがす座頭金(がね)」
- 第14話「蔦重瀬川夫婦道中」
- 第15話「死を呼ぶ手袋」
- 第16話「さらば源内、見立は蓬莱(ほうらい)」
- 第17話「乱れ咲き往来の桜」
- 第18話「歌麿よ、見徳は一炊夢(みるがとくはいっすいのゆめ)」
- 第19話「鱗(うろこ)の置き土産」
- 第20話「寝惚(ぼ)けて候」
- 第21話「蝦夷桜上野屁音(えぞのさくらうえののへおと)」
- 第22話「小生、酒上不埒(さけのうえのふらち)にて」
- 第23話「我こそは江戸一利者なり」
- 第24話「げにつれなきは日本橋」
- 第25話「灰の雨降る日本橋」
- 第26話「三人の女」
- 第27話「願わくば花の下にて春死なん」
- 第28話「佐野世直大明神」
- 第29話「江戸生蔦屋仇討」(えどうまれつたやのあだうち)
- 第30話「人まね歌麿」
- 第31話「我が名は天」
- 第32話「新之助の義」
- 第33話「打壊演太女功徳」(うちこわしえんためのくどく)
- 第34話「ありがた山とかたじけ茄子(なすび)」
- 第35話「間違凧文武二道」(まちがいだこぶんぶのふたみち)
- 第36話「鸚鵡(おうむ)のけりは鴨(かも)」
- 第37話「地獄に京伝」
- 第38話「地本問屋仲間事之始」
- 第39話「白河の清きに住みかね身上半減」
- 第40話「尽きせぬは欲の泉」
- 第41話「歌麿筆美人大首絵」
- 第42話「招かれざる客」
- 第43話「裏切りの恋歌」
- 第44話「空飛ぶ源内」
- 第45話「その名は写楽」
- 第46話「曽我祭の変」
- 第47話「饅頭(まんじゅう)こわい」
- 最終回(48話)「蔦重栄華乃夢噺」
- 【べらぼう】あらすじ概要
- 【べらぼう】なぜ蔦屋重三郎はヒットメーカーに?
- 【べらぼう】蔦屋重三郎とTUTAYAの関係
- 【べらぼう】蔦屋重三郎の年表
【べらぼう】ネタバレあらすじを最終回まで!
2025年の大河ドラマは【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜】。江戸時代中期が舞台で、吉原で育った“蔦重”こと蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)(横浜流星)が、「江戸のメディア王」として時代の寵児へと駆け上がる波瀾万丈の物語!
大河ドラマ【べらぼう】のネタバレあらすじを最終回まで紹介していきます。
第1話「ありがた山の寒がらす」
安永2(1773)年。三日三晩、江戸の町を焼き尽くし、死者が1万人を超えた「明和の大火」から1年半が過ぎた頃、吉原の人々を火災から救った蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)は、茶屋で働く傍ら貸本業を営んでいた。ある日、蔦重は幼なじみの花魁・花の井(小芝風花)から、元高級女郎の朝顔(愛希れいか)への届け物を託される。朝顔が暮らす浄念河岸を訪れた蔦重は、ひどく衰弱した朝顔を目にする。蔦重は、吉原の場末である河岸見世の女郎たちの惨状を目の当たりにして思い悩む。
第2話「吉原細見『嗚呼御江戸』」
蔦重(横浜流星)は吉原に集客する案として、吉原の案内本「吉原細見」の売り上げを伸ばそうと、序文を江戸の有名人である平賀源内(安田顕)に執筆してもらうことを思いつく。一方、江戸城内では、一橋治済(生田斗真)の嫡男・豊千代の誕生祝いの宴が盛大に行われる。そこには御三卿をはじめ、田沼意次(渡辺謙)らが集まっていた。
第3話「千客万来『一目千本』」
蔦重(横浜流星)は女性たちから資金を集め、新たな本に着手。本作りに夢中になる蔦重に対し、父代わりの駿河屋(高橋克実)は激怒し、家から追い出してしまう。それでも蔦重は本づくりを諦めず、絵師の北尾重政(橋本淳)の元を訪ねる。そのころ、意次は将軍・徳川家治(眞島秀和)に白河松平家への養子計画について相談を持ち掛ける。
第4話「『雛形若菜』の甘い罠」
女郎たちを花に見立てた新たな本「一目千本」で成功した蔦重(横浜流星)は、呉服店の着物を着た女郎の錦絵を作る計画を立て、店から資金を集めようとするが苦戦。一方、田安治察(入江甚儀)亡き後、田安賢丸(寺田心)は、意次が画策した白河藩への養子計画を撤回するため、松平武元(たけちか)(石坂浩二)にある頼みを命じる。
第5話「蔦に唐丸因果の蔓」
本屋の株仲間に入れず落胆する蔦重(横浜流星)は、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)からお抱えの「改」(あらため)にならないかとう誘いを受ける。だが、版元になることを目指す蔦重はためらう。そんな中、源内(安田顕)の紹介で、商人の須原屋(里見浩太朗)と知り合った蔦重は株仲間について助言を受ける。…。一方、唐丸(渡邉斗翔)の前に、ある男(高木勝也)が現れる。唐丸の過去を知る男は、唐丸を脅し次第に追い詰める。そして、秩父・中津川鉱山では源内らが出資者から罵倒され、平秩東作(木村了)が人質にされてしまう。
第6話「鱗剥がれた『節用集』」
吉原の案内書「吉原細見」だけでなく、新たに挿絵入りの青本を作ろうと考えた蔦重(横浜流星)は、鱗形屋(片岡愛之助)とともにアイデアを考えたりネタ集めに奔走する。そんな中、須原屋(里見浩太朗)から「節用集」の偽版が出回っていると聞いた蔦重はある疑念を抱く。一方、江戸城内では松平武元(石坂浩二)が莫大な費用がかかる日光社参を提案する。田沼意次(渡辺謙)は予算の無駄遣いを理由に将軍・徳川家治(眞島秀和)に中止を訴える。
第7話「好機到来『籬(まがき)の花』」
鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)が偽版の罪で捕まった。その一件を機に、蔦重(横浜流星)は今の倍売れる「吉原細見」を作ることを条件に地本問屋の仲間として加えてもらう約束を取り付ける。しかし、(既得権益を持つ)西村屋(西村まさ彦)ら老舗地本問屋たちが反発し蔦重の新規参入を阻もうとする。
蔦重は情報を加え、編さんを繰り返して細見の内容を詰めていく。そこに花の井(小芝風花)が現れて、ある話を持ち掛ける。
第8話「逆襲の『金々先生』」
蔦重(横浜流星)が新たに手掛けた吉原細見「籬(まがき)の花」は瀬川(小芝風花)の名を載せたことで評判を呼び、売れに売れた。瀬川を目当てに吉原に多くの客が押し寄せる。瀬川は客をさばききれず、他の女郎たち客の相手をすることに。そんな中、瀬川の新たな客として盲目の大富豪の鳥山検校(市原隼人)が現れる。一方、鱗形屋(片岡愛之助)は新作「金々先生栄花夢」で再起をはかる。
第9話「玉菊燈籠(たまぎくどうろう)恋の地獄」
市中の地本問屋たちが吉原と手を切ると言いだし、蔦重(横浜流星)は細見などを作っても、市中で売り広められなくなることを危惧する。そんな中、鳥山検校(市原隼人)が瀬川(小芝風花)を身請けするという話を耳にする。その時、初めて瀬川を思う自分の気持ちに気付いた蔦重は、ある行動に出る。そして新之助(井之脇海)は、思いを寄せるうつせみ(小野花梨)を連れて吉原を抜け出そうと、思い切った計画を立てる。
第10話「『青楼美人』の見る夢は」
瀬川(小芝風花)の身請けが決まり、落ち込む蔦重(横浜流星)。そんな中、親父たちから瀬川の最後の花魁(おいらん)道中に合わせて出す錦絵の制作を依頼される。調査に出た蔦重は、自分の本が市中の本屋から取り扱い禁止になり、捨てられていることを知る。一方、江戸城では意次(渡辺謙)が家治(眞島秀和)から、種姫(小田愛結)を自分の娘にして、将来は家基(奥智哉)と夫婦にする計画を告げられる。発言の裏には家基のある考えがあった。
第11話「富本、仁義の馬面」
「青楼美人合姿鏡」が高値で売れず頭を抱える蔦重(横浜流星)は、親父たちから俄(にわか)祭りの目玉に浄瑠璃の人気太夫・富本午之助(寛一郎)を招きたいと依頼される。りつ(安達祐実)たちと芝居小屋を訪れ、午之助に俄祭りの参加を求めるが、過去に吉原への出入り禁止を言い渡された午之助は、蔦重を門前払いする。そんな中、鳥山検校(市原隼人)が浄瑠璃の元締めだと知った蔦重は、瀬川(小芝風花)のいる検校の屋敷を訪ねねて、瀬川と再会する。
第12話「俄なる『明月余情』」
昨年に続き吉原で行われる俄(にわか)祭り。その企画の覇権を巡り、若木屋(本宮泰風)と大文字屋(伊藤淳史)らの間で戦いの火ぶたが切られた。蔦重(横浜流星)は、30日間かけて行われる祭りの内情をおもしろおかしく書いてほしいと平賀源内(安田顕)に執筆を依頼。すると、朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)はどうかと勧められる。宝暦の色男とも呼ばれている秋田藩留守居役の喜三二の正体は、かつて蔦重も松葉屋で会っていた平沢常富(ひらさわ つねとみ)(尾美としのり)の筆名だった…。
第13話「幕府揺るがす座頭金(がね)」
蔦重(横浜流星)は、留四郎(水沢林太郎)から鱗形屋(片岡愛之助)が再び偽板の罪で捕まったらしいと知らせを受ける。鱗形屋が各所に借金を重ね、その証文の一つが鳥山検校(市原隼人)を頭とする金貸しの座頭に流れ、苦し紛れに罪を犯したことを知る。一方、江戸城内でも旗本の娘が借金のかたに売られていることが問題視され、意次(渡辺謙)は、座頭金(がね)の実情を明らかにするため、長谷川平蔵宣以(中村隼人)に探るよう命じる。
第14話「蔦重瀬川夫婦道中」
鳥山検校(市原隼人)と瀬川(小芝風花)は幕府による当道座の取り締まりで捕らえられ、蔦重(横浜流星)までも同心に連行されてしまう。その後、釈放された蔦重は、大文字屋(伊藤淳史)から五十間道に空き店舗が出ると聞き、独立して自分の店を構えられる可能性を考える。そんな中、いね(水野美紀)からエレキテルが使いものにならないと聞き、源内(安田顕)を訪ねる。源内はエレキテルが売れないのは弥七(片桐仁)のせいだと訴える。
第15話「死を呼ぶ手袋」
ついに蔦重(横浜流星)は吉原で独立し、自分の店「耕書堂」を構える。しかし市中で源内(安田顕)に会うと、様子がおかしい。須原屋(里見浩太朗)や杉田玄白(山中聡)に話を聞くと、源内はエレキテルへの悪評にいらだっているという。一方、大奥総取締・高岳(冨永愛)が田沼意次(渡辺謙)に、家基(奥智哉)に贈る鷹狩り用の手袋を作ってほしいと頼んだ。意次は承諾。その後、鷹狩りに出かけた徳川家治(眞島秀和)の嫡男・家基(奥智哉)が突然倒れてしまい…。意次(渡辺謙)は、蝦夷地の砂金を売り込んできた源内や東作(木村了)に、ある任務を託す。
第16話「さらば源内、見立は蓬莱(ほうらい)」
家基(奥智哉)はそのまま急逝した。しかしその事件は確固たる証拠がないまま幕引きとなってしまう。意次(渡辺謙)は源内(安田顕)に、これ以上家基の事件について詮索を控えることを告げると、源内は激怒する。一方、蔦重(横浜流星)は源内の住む屋敷を訪ねて、正月に出す戯作の新作を依頼するが、源内が奇妙な言動をすることが気になる。そんな矢先、蔦重や意次の元に「源内が人を斬った」という知らせが入る。
※4月27日は『大河ドラマべらぼう ありがた山スペシャル』を放送。
第17話「乱れ咲き往来の桜」
耕書堂は青本など10冊もの新作を一挙に敢行し、蔦重(横浜流星)の目論見通り、認知度が急上昇する。そんな中、うつせみ(小野花梨)と足抜けした新之助(井之脇海)と再会。新之助と話す中で、蔦重は子供が読み書きを覚えるための手習い本である「往来物」に目をつける。一方、意次(渡辺謙)は、相良城が落成し、視察のため三浦(原田泰造)と共にお国入りする。繁栄する城下町を見て、ある考えを思いつき…。
第18話「歌麿よ、見徳は一炊夢(みるがとくはいっすいのゆめ)」
青本の作者を探していた蔦重(横浜流星)は、北川豊章(加藤虎ノ介)という絵師が描いた数枚の絵を見比べるうちに、ある考えが浮かぶ。早速、豊章を訪ねるが、長屋で出会ったのは、捨吉(染谷将太)と名乗る男だった。そんな中、蔦重は朋誠堂喜三二(尾美としのり)に、新作の青本の執筆を依頼する。女郎屋に連泊できる“居続け”という特別待遇を受けて書き始めた喜三二だったが、しばらくして喜三二の筆が止まってしまう。
第19話「鱗(うろこ)の置き土産」
経営難に陥り店を畳むことにした鱗形屋(片岡愛之助)は、鶴屋(風間俊介)や西村屋(西村まさ彦)らと今後について協議していた。その場で、鱗形屋お抱えの作家・恋川春町(岡山天音)は、今後鶴屋で書くことが決まった。蔦重(横浜流星)は市中の地本問屋たちの勢いに対抗するため春町の獲得をねらい、作戦を練っていた。一方、江戸城では知保の方(高梨 臨)が毒による自害騒ぎを起こし、意次(渡辺 謙)は事情を探っていた。
第20話「寝惚(ぼ)けて候」
『菊寿草』で『見徳一炊夢』や耕書堂が高く評価された蔦重(横浜流星)は、須原屋(里見浩太朗)と大田南畝(桐谷健太)の家を訪ねる。そこで近頃、江戸で人気が出ている“狂歌”を知った蔦重は、南畝から「狂歌の会」への誘いを受ける。一方、意次(渡辺 謙)は、家治(眞島秀和)が次期将軍に一橋家の豊千代を、御台所には種姫を迎える意向であることを治済(生田斗真)に伝え、将軍後継問題は決着するかに思われたが…。
第21話「蝦夷桜上野屁音(えぞのさくらうえののへおと)」
蔦重(横浜流星)は、歌麿(染谷将太)と手掛けた錦絵が売れず、さらに鶴屋(風間俊介)で政演(古川雄大)が書いた青本が売れていることを知り、老舗の本屋との力の差を感じていた。そんな中、南畝(桐谷健太)が土山(柳俊太郎)の花見の会に狂歌仲間を連れて現れる。蔦重はその中に変装した意知(宮沢氷魚)らしき男を見かける。一方、意次(渡辺謙)は家治(眞島秀和)に、幕府のため、蝦夷地の上知を考えていることを伝える。
第22話「小生、酒上不埒(さけのうえのふらち)にて」
歌麿(染谷将太)の名を売り込む会で政演(古川雄大)に激しく嫉妬した春町(岡山天音)は、蔦重(横浜流星)の依頼に筆を執らない状況が続いていた。そんな春町を説得しようと喜三二(尾美としのり)と歌麿が春町を訪ねる。一方、誰袖(福原遥)は意知(宮沢氷魚)に、蝦夷(えぞ)地の件で協力する代わりに身請けしてほしいと迫る。そして松前廣年(ひょうろく)に接触を試み、“抜荷”と呼ばれる密貿易の証をつかもうとする。
第23話「我こそは江戸一利者なり」
狂歌で南畝(桐谷健太)の名が江戸中に知れ渡り、蔦重(横浜流星)が手掛けた狂歌の指南書「浜のきさご」などが飛ぶように売れた。耕書堂は江戸で大注目の本屋となり、蔦重も江戸一の目利きと呼ばれる。そんな時、須原屋(里見浩太朗)から日本橋に進出することを勧められる。一方、誰袖(福原遥)は、蝦夷(えぞ)地の駆け引きで、商人を通さず直接オロシャからこはくを買い付けてはどうかと、松前廣年(ひょうろく)を口説こうとする。
第24話「げにつれなきは日本橋」
吉原の親父たちの支援のもと、日本橋に店を購入する準備を始める蔦重(横浜流星)。しかし、丸屋のてい(橋本愛)は、吉原者の蔦重を受け入れず、店の売却を拒否する。蔦重は、東作(木村了)や重政(橋本淳)に何か打開策はないかとたずねるが…。一方、誰袖(福原遥)は抜荷の証をつかめていなかった。意知(宮沢氷魚)は、次の一手に東作と廣年(ひょうろく)をつなぎ、こはくの直取引話で誘いを謀る。
第25話「灰の雨降る日本橋」
柏原屋から丸屋を買い取った蔦重は、須原屋(里見浩太朗)の持つ「抜荷の絵図」と交換条件で、意知(宮沢氷魚)から日本橋出店への協力を取り付ける。そんな中、浅間山の大噴火で江戸にも灰が降り注ぐ。蔦重は通油町の灰の除去のために懸命に働く。その姿に、門前払いしていたてい(橋本愛)の心が揺れ動く。一方、意知は誰袖(福原遥)に心ひかれ始める。廣年(ひょうろく)は、抜荷の件で大文字屋(伊藤淳史)を訪ねる。
第26話「三人の女」
冷夏による米の不作で、米の値が昨年の倍に上昇。奉公人も増え、戯作者たちが集まる耕書堂では、米の減りが早く蔦重(横浜流星)も苦労していた。そこに蔦重の実母、つよ(高岡早紀)が店に転がり込み、髪結いの仕事で店に居座ろうとする。一方、江戸城では、意次(渡辺謙)が高騰する米の値に対策を講じるも下がらず、幕府の体たらくに業を煮やした紀州徳川家の徳川治貞(高橋英樹)が幕府に対して忠告する事態にまで発展する…。
第27話「願わくば花の下にて春死なん」
蔦重(横浜流星)は大文字屋から、意知(宮沢氷魚)が誰袖(福原遥)を身請けする話がなくなる可能性があると聞く。一方、松前道廣(えなりかずき)が蝦夷地の上知を中止して欲しいと一橋治済(生田斗真)に訴えたことで、治済は意次がひそかに進めていた蝦夷地政策を知る。田沼の屋敷では、佐野政言(矢本悠馬)の父・佐野政豊(吉見一豊)が「系図を返せ」と暴れる。
第28話「佐野世直大明神」
城中で意知(宮沢氷魚)が政言(矢本悠馬)に斬られて絶命した。政言は切腹する。後日、意知の葬列が市中を進み、蔦重(横浜流星)たちが見守る中、石が投げ込まれる。騒然とする中、誰袖(福原遥)は棺を庇い駆け出す…。蔦重は亡き意知の無念を晴らす術を考える。そんな中、北尾政演(古川雄大)が見せた絵をきっかけに、仇討ちを題材にした新たな黄表紙の企画を進める。
第29話「江戸生蔦屋仇討」(えどうまれつたやのあだうち)
蔦重(横浜流星)は政演(古川雄大)が持ち込んだ「手拭いの男」の絵を使った黄表紙を作りたいと戯作者や絵師たちに提案する。そこに鶴屋(風間俊介)が現れ、政演を貸すと申し出る。政演は草稿を考え始める。一方、意次(渡辺謙)は、松前家の裏の勘定帳を入手する。蝦夷地で松前家が公儀に秘密裏で財を蓄えていた証拠をつかみ、上知を願い出る準備を始める。
第30話「人まね歌麿」
京伝の黄表紙「江戸生艶気樺焼」(えどうまれうわきのかばやき)が売れ、耕書堂は開業以来の大盛況に。蔦重は狂歌絵本を手掛けるため、歌麿(染谷将太)を起用。その後、蔦重は歌麿ならではの絵を描いて欲しいと新に依頼するも、歌麿は悩み…。一方、松平定信(井上祐貴)は治済(生田斗真)から公儀の政に参画しないかと誘いを受ける。
第31話「我が名は天」
利根川が決壊した。江戸市中が大洪水となる。蔦重は新之助(井之脇海)とふく(小野花梨)を気にかけて深川を訪れる。
食料の配給が行われる寺で、平蔵(中村隼人)に会った蔦重は、幕府が復興対策に追われ、救い米もままならないと聞く。
そんな中、江戸城では意次(渡辺謙)が体調を崩した家治(眞島秀和)からある話を聞かされる。
第32話「新之助の義」
ふく(小野花梨)と子供を失った新之助(井之脇海)の元を訪ねた蔦重は、救い米が出たことを知った。だが長屋の住民たちから田沼時代に利を得た自分への怒りや批判を聞かされる。
御三家は新たな老中に松平定信(井上祐貴)を推挙する意見書を提出。しかし田沼派の水野忠友(小松和重)や松平康福(相島一之)は、老中を辞職し謹慎を続ける意次(渡辺謙)の復帰を画策する。
第33話「打壊演太女功徳」(うちこわしえんためのくどく)
天明7年(1787年)、江戸で打ちこわし(※民衆が商人や名主、金貸しらを襲うこと)が発生。新之助(井之脇海)たちは米屋を次々と襲撃していく。
江戸城では老中たちがその知らせを受けて混乱するが、意次(渡辺謙)は冷静沈着に提言する。蔦重は意次に米の代わりに米を買える金を配るよう進言する。
一方、一橋邸では治済(生田斗真)が定信(井上祐貴)に、大奥が反対を取り下げて、正式に定信の老中への就任が決まると告げる。
【べらぼう】33話あらすじと感想!新之助の最期に「素晴らしい人生」「幸せだった」と反響 | dorama9
第34話「ありがた山とかたじけ茄子(なすび)」
老中首座に抜擢された定信(井上祐貴)は、質素倹約を掲げ、厳しい統制を敷き始める。 そんな中、蔦重(横浜流星)は狂歌師たちに、豪華な狂歌絵本を作ろうと呼びかける。しかし、そこに現れた南畝(桐谷健太)は、筆を折ると宣言。南畝は定信を皮肉った狂歌を創作した疑いで処罰の危機にあった。意次(渡辺謙)が作った世の空気が定信の政によって一変する中、蔦重は世の流れに抗うため、ある決意をもって、意次の屋敷を訪れる。
【べらぼう】34話の感想!誰袖(福原遥)の処分「押込の刑」って何? | dorama9
第35話「間違凧文武二道」(まちがいだこぶんぶのふたみち)
定信(井上祐貴)の政を茶化した「文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくどおし)」。しかし、これを目にした定信は勘違いをし、逆に改革が勢いづく結果となり、蔦重(横浜流星)は複雑な気持ちになる。そんな中、読売で、定信が将軍補佐になったことを知る…。歌麿(染谷将太)は、かつて廃寺で絵を拾い集めてくれたきよ(藤間爽子)と再会し、心に変化が生まれる。江戸城では、家斉(城桧吏)が大奥の女中との間に子をもうける。
【べらぼう】35話の感想!石燕が見た雷獣は源内先生?! | dorama9
第36話「鸚鵡(おうむ)のけりは鴨(かも)」
蔦屋の新作『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』『天下一面鏡梅鉢(てんかいちめんかがみのうめばち)』が飛ぶように売れる。定信(井上祐貴)は、自身の改革を風刺する蔦重(横浜流星)が手がけた本に激怒し、絶版を言い渡す。喜三二(尾美としのり)は、筆を断つ決断をし、春町(岡山天音)は呼び出しにあう。そして蔦重は、南畝(桐谷健太)からの文で、東作(木村了)が病だと知り、須原屋(里見浩太朗)や南畝とともに、見舞いに訪れる。
【べらぼう】36話の感想!春町の豆腐の角に頭ぶつけた最期にネット反響 | dorama9
第37話「地獄に京伝」
武士でありながら戯作者でもあった春町(岡山天音)は自害。同じく武士の喜三二(尾美としのり)も江戸から去るなど、蔦重お抱えの戯作者たちがいなくなり、北尾政演(古川雄大)も執筆を躊躇する。そのころ、歌麿は栃木の商人からある肉筆画の依頼を受け、その喜びをきよ(藤間爽子)に報告するが…。
一方、定信(井上祐貴)は、大奥への倹約、借金を抱える旗本、御家人を救済するため、札差に債務放棄をさせる棄損令、中洲の取り壊しを実行する。その煽りを受けた吉原のため、蔦重は政演や歌麿に新たな仕事を依頼するが、てい(橋本愛)がその企画に反対する。
【べらぼう】37話あらすじと感想!蔦重、政演と喧嘩別れに | dorama9
第38話「地本問屋仲間事之始」
蔦重(横浜流星)は、歌麿(染谷将太)のもとを訪ねると、体調を崩し、寝込むきよ(藤間爽子)の姿があった…。そんな中、蔦重は鶴屋(風間俊介)のはからいで、口論の末、けんか別れした政演(京伝)(古川雄大)と再び会うが…。一方、定信(井上祐貴)は平蔵(中村隼人)を呼び、昇進をちらつかせ、人足寄場を作るよう命じる。さらに定信は、改革の手を緩めず、学問や思想に厳しい目を向け、出版統制を行う。
【べらぼう】38話あらすじと感想!きよの死去に「ペニシリンがあれば」の声 | dorama9
第39話「白河の清きに住みかね身上半減」
地本問屋の株仲間を発足させた蔦重(横浜流星)は、改めを行う行事たちをうまく丸め込み、山東京伝(政演)(古川雄大)作の三作品を『教訓読本』として売り出した。一方、きよ(藤間爽子)を失い、憔悴した歌麿(染谷将太)は、つよ(高岡早紀)とともに江戸を離れる。年が明け、しばらくの後、突然、蔦屋に与力と同心が現れ、『教訓読本』三作品について絶版を命じられ、蔦重と京伝は牢屋敷に連行されてしまう…。
【べらぼう】39話あらすじと感想!てい(橋本愛)のビンタにネット反響 | dorama9
第40話「尽きせぬは欲の泉」
身上半減の刑を受けた蔦重(横浜流星)は、営業を再開し、執筆依頼のため京伝(政演)(古川雄大)を訪ねる。妻の菊(望海風斗)から、滝沢瑣吉(さきち)(津田健次郎)の面倒をみて欲しいと託される。蔦重は手代扱いで店に置くが、瑣吉は勝川春章(前野朋哉)が連れてきた弟子・勝川春朗(くっきー!)と喧嘩になり…。蔦重は歌麿(染谷将太)の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かう…。
【べらぼう】40話あらすじと感想!歌麿(染谷将太)の美人画始まりの回 | dorama9
第41話「歌麿筆美人大首絵」
蔦重(横浜流星)が、処分を受けた須原屋(里見浩太朗)を訪ねると、須原屋は二代目に店を譲り引退すると言う。そして蔦重は、歌麿(染谷将太)と「婦人相学十躰」の売り出し方を思案する。そんな中、つよ(高岡早紀)の身体に異変が起きる。一方、城中では家斉(城桧吏)の嫡男・竹千代が誕生。定信(井上祐貴)は、祝いの場で突然、将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出る。家斉や治済(生田斗真)は動揺するが…。
【べらぼう】41話あらすじと感想!「おっかさん」トレンド入り | dorama9
第42話「招かれざる客」
蔦重の母のつよ(高岡早紀さん)がこの世を去った。蔦重(横浜流星)は最期に間に合わなかった。
歌麿(染谷将太)の美人大首絵で持ち直し、書物問屋も始めた蔦重(横浜流星)は、年が明けて身上半減から店を立て直した。歌麿の新作、江戸の「看板娘」を描いた錦絵も大評判となり、看板娘に会いたい客で各店は繁盛、江戸の町も活気づいていた。
「難波屋」では、きた(椿)が出す茶の値が一杯4文から48文にはね上がり、「高島屋」でもおひさ(汐見まとい)が焼く煎餅に太客が列をなし、吉原でも芸者の豊ひな(門脇遥香)への指名が殺到。※現代のAKB48のような、元祖「会いに行けるアイドル」のようなものか。
そんなある日、蔦重の店に人相見・大当開運(太田光/爆笑問題)がやって来る。開運は「実は、相学仲間が蔦屋さんに会いたいと…」と言って、観相家(田中裕二/爆笑問題)を紹介。観相家は「『婦人相学十躰』いいですね」と歌麿の絵を絶賛し、蔦重に店の奥へと案内された。
そんな中、てい(橋本愛)は蔦重に“子ができた”と告げる。一方、定信(井上祐貴)は、オロシャ問題や朝廷の尊号一件に対する強硬姿勢で、幕閣内で孤立し始めていた。
歌麿は美人画シリーズを出すために大量の絵を描かねばならず、そのノルマをこなすために蔦重は弟子に描かせて名だけ入れろと言い出し複雑な思いだ。。そのころ、西村屋(西村まさ彦)が二代目・万次郎(中村莟玉)を伴い、錦絵を出さないかと歌麿に接触。「蔦重の抱えだから」と西村屋の提案を拒否していた歌麿だが、万次郎が持参した「当世美男揃」「白黒錦絵」といった魅力的なアイデアに胸を高鳴らせる。西村屋は蔦屋の下に歌麿の署名があるのはおかしい、順番が逆ではないのかと指摘し、「騙されているとは申しませんが、(蔦重に)都合よく使われているのでは?」と忠告する…。
幕府は吉原の女郎を除き、個人名を絵のなかに記すことを禁じる。
そんな中、吉原に借金のある蔦重が、吉原の親父衆との間で、入銀なしで絵を作り、蔦重の借金100両を歌麿の絵50枚で返す話を歌麿のいないところで勝手にまとめた。歌麿は「借金のかたに俺を売ったってこと?」と怒った。
ラスト、歌麿は西村屋の仕事を受けるとし「もう蔦重とは終わりにします」ときっぱりと話した。
第43話「裏切りの恋歌」
蔦重(横浜流星)は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿(染谷将太)が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重だったが、ある日、歌麿が西村屋の万次郎(中村莟玉)と組む話をきき動揺する。
蔦重が歌麿の元に行くと、歌麿は恋心を秘めた女絵を描いていた。その恋心は野暮な蔦重にまったく伝わらない。歌麿は「蔦重とは、もう組まねえ」と宣言。決別の気配が漂う中、てい(橋本愛)が産気づく。産婆(榊原郁恵)がやってきて、産むしかないという。早産になり子供が生きられない。ていは蔦重に子供を育てることを願っていたが、母体に危険が迫っているため、産むしかなくなる。部屋の外に出た蔦重は祈るばかり。
一方、江戸城では、定信(井上祐貴)がオロシャ対策に全力を注いでいた。長崎への通行を許可したことで遣日使節であるラクスマンを帰国させることに成功。将軍・家斉(城桧吏)は定信が将軍補佐から外れてもこれまでと同じように指示を出す仕組みはないものかと話していた。その家斉に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙う定信だが…。
家斉は定信の将軍補佐、および老中の役目を解くと「これよりは政には関わらず、ゆるりと休むが良い」と言い渡す。徳川宗睦(榎木孝明)が「越中守をおいて他にこの難しき形勢を乗り切る者はいない」とフォローしたが、定信の家臣・本多忠籌(矢島健一)、松平信明(福山翔大)らはすでにオロシャの件は定信が方をつけ、さらに質素倹約によって幕府に貯金もできたという。家斉の父・一橋治済(生田斗真)も含め、グルになって定信を厄介払いした。
布団小屋にて、定信は「嫌がられようとも煙たがられようともやるべきことをやり通したのはわたくしではないか!」「くずどもが…地獄へ…地獄へ落ちるがよい」と怒った。その後、同じく治済に力を封じられた大奥総取締・高岳(冨永愛)が定信に接触。治済がかつて暗殺に用いたとされる“死の手袋”を差し出した。(つづく)
第44話「空飛ぶ源内」
蔦重(横浜流星)の前に、耕書堂で本を書かせて欲しいと、駿府生まれの貞一(井上芳雄)と名乗る男が現れる。貞一は源内(安田顕)が作ったという相良凧を持っていて、源内が生きているのではと考え始める。その後、玄白(山中聡)や南畝(桐谷健太)、重政(橋本淳)らと会い、源内の謎を追い続ける。そして源内が描いた「西洋婦人画」を手に入れた蔦重は、街中で源内に似た人も見かけた…。一方、歌麿(染谷将太)は吉原で、本屋に対して派手に遊んだ順に仕事を受けると豪語し座敷で紙花をばらまいていた…。
そんな中、てい(橋本愛)が蔦屋耕書堂の戸口で「一人遣傀儡石橋」という草稿を見つける。そこには、源内本人が書いたものと思われる「死を呼ぶ手袋」のその後が記されており、寺の名前と日時が指定された紙が挟まっていた。蔦重は指定の日に安徳寺を訪れた。そこには三浦庄司(原田泰造)、長谷川平蔵(中村隼人)、松平定信(井上祐貴)、高岳(冨永愛)らが待ち受けていた。蔦重は、あの殺人事件の証拠である、“故徳川家基の手袋”を見せられ、「傀儡好きの大名」を討つ仲間に誘われる。
第45話「その名は写楽」
定信(井上祐貴)らに呼び出された蔦重(横浜流星)は、傀儡好きの大名への仇討ちに手を貸すよう言われる。芝居町に出向いた蔦重は、今年は役者が通りで総踊りをする「曽我祭」をやると聞き、源内が書いたとしか思えない役者絵を出すことを思いつく。
蔦重は、南畝(桐谷健太)や喜三二(尾美としのり)らとともにその準備を進めていく。画号を考える中、「“しゃらくさい”ってのはどうかね?」と口を切ったのが朋誠堂喜三二(尾美としのり)。蔦重は「この世の楽を写す」あるいは「ありのままを写すことが楽しい」という意味を込め、「写楽(しゃらく)」に決定。
一方、歌麿(染谷将太)は、自分の絵に対して何も言わない本屋に、苛立ちを感じていた…。そんな歌麿に対し、ていは「余所にも素晴らしい本屋はおりましょう。 けれど、かように歌さんのことを考え抜く本屋は。二度と現れぬのではございませんか? 二人の男の業と情、因果の果てに生み出される絵というものを見てみたく存じます」と訴える。
第46話「曽我祭の変」
蔦重(横浜流星)は納得する役者絵が仕上がらず行き詰まっていた…。そんな中、蔦重と歌麿(染谷将太)、2人にしか生み出せない絵を見てみたいと訴えるてい(橋本愛)。この思いに突き動かされ、歌麿が再び耕書堂に戻ってくる。その後、役者絵は完成した。松平定信(井上祐貴)は「画号は『東洲斎写楽』とせよ。 写楽は東洲、江戸っ子。これは江戸の誉としたい」と蔦重に伝えた。
歌舞伎の興行「曽我祭」に合わせて、蔦重は絵師・東洲斎写楽の名で絵を売り出す!“グニャ富”こと中山富三郎(坂口涼太郎)は自分の絵にギョッとし、「わたしゃ、こんなふうに描くなんて、聞いてないよ!」と蔦重に抗議する。この騒動も追い風となって、写楽のうわさは、徐々に江戸市中、江戸城中にも広まっていく…。
人々は写楽の正体について推測し始める。さらに生前、源内と親交が深かった杉田玄白(山中聡)が「これは源内の絵だ」と言い始めたことで、狙い通り平賀源内生存説が江戸中を駆け巡った。
定信の間者(かんじゃ)となった大崎(映美くらら)が治済に“死を呼ぶ手袋”の真相が書かれた「一人遣傀儡石橋」を見せ、源内生存説に信ぴょう性を持たせる。さらに、大崎は源内が芝居町にある浄瑠璃小屋に潜んでいると嘘の報告をし、治済とともに曽我祭に足を運ぶ。
しかし、治済は筆跡から「一人遣傀儡石橋」を書いたのが源内ではなく定信であること見抜いていた。ではなぜ、芝居町まで足を運んだのか。それは定信らへの“警告”のためだった。
治済から手渡された饅頭を大崎は恐れながら食べることに。大崎は亡くなった。治済が祝儀の饅頭に紛れ込ませていた毒饅頭は、定信らが待機していた浄瑠璃小屋、そして蔦重の店にも届けられた。無差別ではなく、定信らを狙った犯行だった。
蔦重は巻き込まれたことで定信らに怒る。だが、定信は蔦重に隠し玉を見せる。それは善良そうな顔付きだが治済とうり二つの人物(生田斗真/一人二役)だった。(つづく)
第47話「饅頭(まんじゅう)こわい」
定信(井上祐貴)や平蔵(中村隼人)たちのあだ討ち計画は、治済(生田斗真)に気付かれる。治済は毒まんじゅうで大崎(映美くらら)を死に追いやり、定信たちは追い詰められる。
実は、定信は治済の替え玉の人間を用意していた。治斉が突然消えては周りに不審がられるための策だ。前回のラストに登場した人物こと、能役者の斎藤十郎兵衛(生田斗真、二役)だ。蔦重はあまりに似ているので驚いた。
耕書堂に届いた毒まんじゅうで手代・みの吉(中川翼)が倒れてしまう。いつまた命を狙われるとも限らないため、しばらく店を閉める羽目に。一時的に店を閉めた蔦重(横浜流星)だったが、定信のもとを訪ね、治済の息子で時の将軍・家斉(城桧吏)を巻き込んだ驚きの策を提言。それは治済に毒まんじゅうを食べさせること。それができるのは将軍・家斉しかいない、という提案だった。
あだ討ち計画は再び動きだし、定信は、徳川家治(眞島秀和)の異母弟で体調を崩していた清水重好(落合モトキ)のもとを訪ねる…。
重好は家治が死の間際、「悪いのは父だ。すべて、そなたの父だ」と家斉に言い、「天は見ておるぞ、天は、天の名を騙るおごりを許さぬ!」と治斉に告げ、幼い家斉に錯乱を装って治済の悪行を伝えようとしていたことを覚えていた。
清水は、それを家斉にも思い出させようとするが、治済の邪魔が入る。
しかし、「おいたわしや…もはや中納言様は夢か現もお分かりにならぬように…」と治済が言った。その言葉は家斉が幼少期に聞いたものだった。家斉の脳裏に家治の最期が蘇った。
家斉は父の悪事を確信した。さらに、亡き大崎の手紙が家斉の背中を押した。(※耕書堂の出店に立ち寄った際、密かに家斉への手紙を蔦重に託していた。)
大崎は、「どうかお父上様の悪行をお止めください。あの方を止められるのはこの世でただお一人。上様しかいらっしゃいません」と書き残していた。家斉は覚悟を決めた。
家斉は、清水重好の茶室に父・治済を呼び出す。しかし治斉は差し出された饅頭を口にしない。家斉は治済の分まで饅頭を美味しそうに食べた。次に、家斉が飲んだお茶が治斉に回ってきた。さすがにこのお茶を治済は飲んだ。
直後、家斉が倒れ込む。治斉は「まさか、(家斉と)もろともに…!」と気づいた。だが時すでに遅し。治済もすぐに意識を失った。
実は、睡眠薬だった。蔦重は栗山(嶋田久作)から「どれほど外道な親であっても、親殺しは大罪。義はあっても、上様は大罪を犯すことになり、それを仕掛けた私たちも外道に成り下がる」と言われた。そこで生かすことにした。本物の治済は阿波の孤島に閉じ込め、斎藤十郎兵衛(生田斗真、二役)が治済になりすますことに…。
生田斗真が一人二役を演じた「斎藤十郎兵衛」は東洲斎写楽の正体として学者の間で最も有力視されている人物です。しかし本作では写楽の複数人説を取りました。そんな中、斎藤十郎兵衛が意外な役割で物語に登場。学者たちは批判したいでしょうが、面白いストーリー展開ですね。
無事に仇討ちを終えた定信は国へ戻るにあたって、最後に耕書堂に立ち寄る。春町に凧を上げさせて死に追いやってしまった蔦重と、上がった凧を許して笑う余裕を持てなかった定信。どちらも苦しみを抱えていた。そんな中、 「ご一緒できてようございました」と頭を下げた蔦重に、定信は今後は自分のもとに良い書を送るよう命じた。
白河に戻った定信は民の暮らしの向上に努め、自らを“楽翁”と名乗って文化活動に勤しんだという。(つづく)
最終回前の47話で、ラスボスといっていい治済(生田斗真)との対決がついに決着しましたね。治済が替え玉に置き換えられ、本物は孤島へ…。史実では治済が替え玉だった証拠がないようです。さすがに事実ではなさそうだけれど、逆転劇の仇討ちで、とても面白かったですよ。
最終回(48話)「蔦重栄華乃夢噺」
放送日:12月14日 日曜 20:00 -20:59 NHK総合
平賀源内と天罰
一橋治済(生田斗真)は松平定信(井上祐貴)らの企てにより、孤島に送られることに。しかし彼はその道中で“用を足したい”と要求し、箱の外に出させてもらう。そして、見張りの腰から刀を抜き取って刺し、逃走。
治済は「待っておれよ…。傀儡(くぐつ)ども!」と叫びながら、刀を抜いた。そこで、雷に打たれて亡くなってしまう治済。彼の亡骸の横には平賀源内(安田顕)を思わせる髷(まげ)の男が立っていた。
瀬川(福原遥)の現在
源内と同じく人気キャラ・瀬川(小芝風花)のその後も描かれる。自由の身となった瀬川は、蔦重の夢を応援するため、そして「瀬川」という名跡を背負った使命を果たすため、姿をくらませた瀬川。
磯八と仙太は長谷川平蔵宣以(中村隼人)のために瀬川の行方を調べていた。そして、瀬川は駕籠屋(かごや。江戸時代に街道にあった駕籠の宿場所)の女将として暮らしていて、大好きな本に囲まれ、子どもにも恵まれ、幸せに暮らしていることが分かった。
蔦重は少し離れた場所から瀬川を見守り、涙ぐむ。
写楽は誰か?
店を再開した蔦重(横浜流星)は写楽絵をしばらく出し続け、精力的に商売と向き合う。
江戸では、“写楽は誰か?”という話題で持ちきりになっている。写楽の絵の制作に携わった絵師・作家の名前、さらには亡き恋川春町(岡山天音)の名前も写楽として挙がっている。
そうした中、北尾重正(橋本淳)が「蔦重。写楽は歌(=歌麿)だってなぁ言わねえのかい? いっち骨を折ったのは歌じゃねえか」と問いかける。歌麿(染谷将太)は「う~ん…俺の絵って言われても しっくりこねえし 皆が「写楽」」と返答する。
一方、阿波徳島藩主蜂須賀家お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛(生田斗真/二役)は「治済」になりすまして日々を過ごしていた。そんな中、治済が亡くなったことを知らされる十郎兵衛。蔦重は十郎兵衛を自由にしても良いと指摘するが、すでに戻る場所はなかった。そのとき、蔦重は「東洲斎」の漢字三文字を入れ替えて読んでみると「さい、とう、じゅう」となることに気づいた。
蔦重は、「東洲斎写楽」に関わった仲間に、「陰で骨を折ってくださった方」として十郎兵衛の存在を伝え、漢字三文字の入れ替えを明かした。その上で、蔦重は仲間に「このお方も後の世で写楽の一人って名があがるような仕掛けができねえかって」と相談する。
写楽の正体は斎藤十郎兵衛…というのが2025年時点で一番有力な説です。もちろん脚本の森下佳子さんも知っていて、こうして写楽=斎藤十郎兵衛説と混ぜ合わせてたのでしょう。辻褄合わせがうまいですね。
*森下佳子さんが「写楽複数人説」を採用した件のコメント↓
「もちろん、美術史の世界では、いまは一応、(斎藤十郎兵衛が正体で)決着しているということは存じ上げてはいたのですが。それでも写楽の絵をざーっと並べて見たときに、複数人説の方がしっくりくるなと思ったんで。すごい短い期間にものすごい数の作品を出していて、しかもあれを一気に出したとしたら、ものすごい短時間で準備しなくてはいけない。果たしてこれを一人でやったのかというのが結構、疑問だったと。2期の写楽の絵って全身像になるのですが、1期で描いた顔をコピペしたみたいで。そういったところからも『これ何人かで手分けしたんじゃないか』って気がして。複数人説を採ろうというのは初めから決まっていました」
歌麿がこの世の仲間入り
歌麿はてい(橋本愛)に、「俺ゃ 望まれない子でね…。けど 写楽の絵にゃあ みんなが溶け合ってんじゃねえですか。俺も その一部ってえか…。鬼の子も この世の仲間入りして いいんですよって言われてるみたいでさ」と、胸の内を明かす。
歌麿は母から「鬼の子」と言われて、苦しんで生きてきたが、自分の存在を肯定できるようになったようだ。
蔦重の精力的な仕事
更にその後、伊勢松坂に住む医者であり国学者の本居宣長(北村一輝)による和学の分野の出版にも手を広げようとする蔦重。
手代を連れて伊勢松坂に向かった蔦重は、しぶる本居に和学を大事にしてきた定信(井上祐貴)に頼んだ文(ふみ)を渡して説得をした。
本居の承諾を得た蔦重は、帰り道の茶店で聞いた読者の意見を参考に、馬琴(津田健次郎)には長編を、一九(井上芳雄)には江戸に縛られない話を書くようにも頼んだ。
その依頼によって、馬琴が「南総里見八犬伝」、一九は「東海道中膝栗毛」という名作を生み出すことになる。
最期まで書を持って世を耕し続ける
ある日、蔦重は脚気(かっけ)の病に倒れてしまう。脚気はビタミンB1不足による神経障害で、当時は死に至る病だった。
てい(橋本愛)や歌麿(染谷将太)たちが心配する中、、蔦重は「もうすぐ死ぬやつが必死で作ったってなりゃ、『ひとつ買っといてやるか』ってなんじゃねえかって」と一儲けにつなげようとする。ていは、食事をきちんと取ることや無理をしないことなどを約束させて、仕事をすることを許した。
蔦重はこの世にやり残したことがないように、周囲との別れを意識して、仲間たちと本づくりをすることに…。
蔦重は、「死んだあと、こう言われてぇのでございます。『あいつは本を作り続けた。死の間際まで、書をもって世を耕し続けた』って。皆さま、俺のわがままを聞いちゃもらえねぇですか」と、政演(古川雄大)や重政(橋本淳)、南畝(桐谷健太)、喜三二(尾美としのり)ら仲間に新作を頼んだ。そうして病の中でも、書を以って世を耕し続ける蔦重。
また、歌麿には「新しい女絵」を依頼する。歌麿は母を色っぽい山姥に、自分を金太郎にした絵を描いて、蔦重に「おっかさんと こうしたかったってのを二人に託して 描いてみようかと思って」と説明した。
蔦重の最期
蔦重は、ある夜、不思議な夢をみた。九郎助稲荷(くろすけいなり)(綾瀬はるか)が巫女にふんして、蔦重の前に現れ、「今日の昼九つ、午の刻(※12時)に迎えに来ます」と死のお告げを伝える。拍子木の音が合図だという。
いよいよその時が来る。ていは、二代目のこと、仕事の頼み先のこと、さらに通夜から戒名のことまで準備万端に整えていた。さらに、ていは「『笑い』という名の富を、旦那様は日の本中にふるまったのではございませんでしょうか。雨の日も風の日もたわけきられたこと、日の本一のべらぼうにございました」と蔦重に語った。
歌麿をはじめ仲間たちが次々に駆け付けてきた。午の刻を知らせる鐘の音が鳴る。蔦重は、ていの胸の中で「ありがた山の寒が(らす)…」と言い切らぬうちに目を閉じてしまう。
太田南畝(桐谷健太)は、「呼び戻すぞ! 蔦重!」と大きな声で叫び、「俺たちは へ(屁)だ~!」という。一同が「へ!へ!へ!へ!へ!へ!」と盛大にコールしながら、蔦重の周囲で踊る。
蔦重が「拍子木…聞こえねぇんだけど」という。一同が「へ?」とビックリした。そんなクスっと笑える場面で、拍子木が鳴り、本篇の幕が閉じる。エンドロールが流れて全編終了へ。(終わり)
*蔦重の最期は、蔦重の墓碑に書き残された記録に基づいて描かれています↓
寛政八年、重病を患い危篤。寛政九年夏、五月六日、彼は「自分は昼時には死ぬだろう」と言った。没後の蔦屋の諸事について整理し、妻と別れの言葉を交わして最期の時を待った。昼時になり「まだ拍子木が鳴らないな。どうしてこんなに遅いのか」と笑った。そう言った後、再び口を開くことはなく、夕刻ついに亡くなる。享年四十八。正法寺に葬る。 参照「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式X(https://x.com/berabou_nhk/status/2000172679782072738)
ついに【べらぼう】がフィナーレ。最終回では源内先生の存在がほのめかされ、瀬川の幸せなその後が描かれて、ここまで見続けた視聴者には嬉しい展開でした。
最後の「へ」のコールが、おかしくも、切なさも、愛も感じる不思議な味わいのシーンでした。蔦重が最後に拍子木が鳴らないことに触れる台詞は史実のようですが、悲しみで終わらせなくて、本作にピッタリで良かったですよ。
【べらぼう】あらすじ概要
- 時は18世紀半ば。
- 舞台は、人口100万を超え、天下泰平の中、世界有数の大都市に発展した江戸。
- 主人公は、多くの浮世絵師・作家の才能を世に送り出した出版人「蔦屋重三郎」(つたやじゅうざぶろう)。※実在の人物です。
貸本屋からヒットメーカーへ
蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)は、江戸郊外の吉原の貧しい庶民の家に誕生。幼いころに両親と生き別れ、引手茶屋・駿河屋の養子となる。 蔦重は、貸本屋から身を興し、書籍の編集・出版業へ。
当時、時の権力者・田沼意次(渡辺謙)が創り出した自由な空気の中、江戸文化が花開き、平賀源内(安田顕)など多彩な文人が輩出されていました。
蔦重は、朋誠堂喜三二(平沢常富の筆名)などの文化人たちと交流を重ね、「黄表紙本」という挿絵を使った書籍でヒット作を次々と送り出します。
江戸の出版王へ
33歳の蔦重は商業の中心地・日本橋に耕書堂を開業。“江戸の出版王”へと成り上がっていきます。蔦重は、喜多川歌麿(染谷将太)、山東京伝、葛飾北斎、曲亭馬琴、十返舎一九といった若き個性豊かな才能たちをが見いだしました。
出版統制令
時世は移り変わり、田沼意次が失脚。代わりに台頭した松平定信は寛政の改革を実施し、1790年には幕政批判や風紀を乱す書物と書き手を取り締まる「出版統制令」を発令します。翌1791年に戯作者の山東京伝の洒落本が風俗を乱したとして罰せられ、彼と親交の深かった蔦重も財産の半分を没収される処罰を受けます。周囲では江戸追放や死に追いやられる者も…。
蔦重の晩年
蔦重は、その後も幕府からの執ような弾圧を受け続けま。それでも反権力を貫き通し、戦い続けた蔦重。そんな中、蔦重の体を病魔が襲います。 命の限りが迫る中、蔦重は壮大なエンターテインメントを仕掛けます。それは浮世絵師・東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)の企画・プロデュースです。
歌麿、写楽、北斎…。名前と作品は知ってるけど、版元・蔦屋重三郎のことは知らなかった。知られざる物語を知れるの楽しみ♪
【べらぼう】なぜ蔦屋重三郎はヒットメーカーに?
2025年の大河の主人公・蔦屋重三郎は、吉原のガイドブックをヒットさせ、「美人画」の喜多川歌麿、「役者絵」(歌舞伎絵)の東洲斎写楽という2大スターを生み出した(企画編集・制作を行う)江戸のヒットメーカー。江戸のメディア王とも称されています。
気になるのは、なぜ蔦屋重三郎はヒットメーカーになったのか?という疑問。
もちろん大河ドラマを視聴することで、分かっていくのですが…。実在する人物なので評伝や解説本がたくさん出ています。その中で、分かりやすく7つのポイントを挙げている書籍がありました。
伊藤賀一氏(「スタディサプリ」日本史講師)が著者『これ1冊でわかる! 蔦屋重三郎と江戸文化: 元祖・敏腕プロデューサーの生涯と江戸のアーティストたちの謎を解き明かす』の中で、以下の7つのキーワードを挙げています↓
蔦屋重三郎が成功した(ヒットメーカーになった)7つのキーワード
- 『出自』を活かした。
- 『家庭の事情』を活かした。
- 『競合相手の失敗』を活かした。
- 『流行(ブーム)』を活かした。
- 『業界への弾圧』を活かした。
- 『みずからの死』を活かした。
- 『時代背景』を活かした。
出自(親ガチャ)を活かす
特に、出自や家庭事情を活かした点は興味深いです。伊藤氏は、蔦屋重三郎について「現代社会では『ガチャ』と呼ばれるような、みずからは選べない偶発的要素を前向きに活かし、たくましくなり上っていった人物だ」と評しています。
弾圧に屈しない
業界への弾圧に屈しなかったのも特筆すべき点。寛政の改革による出版統制令の影響で、戯作の黄表紙や洒落本が発売禁止処分になり、狂歌絵本も一時的に停滞。それでも、蔦重は浮世絵や専門書、学術書に活路を見出し、話題になりました。
閉塞感が漂う時代に壁を突破
また、江戸の人々は物価高に振り回されながらも、ゆるい世を謳歌し、出版業界は隆盛を迎えました。
実質賃金が上がらなくて閉塞感が漂う現代。現状を時代や政治のせいや、親ガチャのせいにして嘆いて、後ろ向きに生きていても壁を突破できません。現代を生きる我々にも、蔦屋重三郎から色々と学べるところは多いかもしれませんね。
【べらぼう】蔦屋重三郎とTUTAYAの関係
TUTAYA(蔦屋書店)は重三郎の子孫が経営してるの?と気になりますね。
実は、蔦屋重三郎とTUTAYA(蔦屋書店)は関係ありません。
TUTAYA(蔦屋書店)は蔦屋重三郎の子孫が経営しているわけではありません。
TSUTAYAを創業したのは増田宗昭(ますだむねあき)さんですが、その増田さんの祖父が営んでいた置屋の屋号が「蔦屋」だったことに由来して、蔦屋書店と名付けられたそうです。
なお、その祖父の屋号は、蔦屋重三郎の業績にあやかった命名であるとされています。
【べらぼう】蔦屋重三郎の年表
大河ドラマ【べらぼう】の主人公・蔦屋重三郎の年表(大河ドラマとの対応表)です↓
| ドラマ | 年代・蔦重の年齢 | 蔦屋重三郎の出来事 |
|---|---|---|
| 寛延3年1月7日(1750年2月13日)・0歳 | 誕生(遊郭の街である新吉原で産まれた) | |
| 1話 | 安永2年(1773年)・23歳 | 本屋「書肆耕書堂」を営む |
| 2話 | 安永3年(1774年)・24歳 | 『細見鳴呼御江戸』編纂に携わる |
| 3話 | 安永3年(1774年)・24歳 | 「蔦屋」の名で初めて北尾重政を絵師に起用した『一目千本』を刊行 |
| 安永4年(1775年)・25歳 | 自ら『籬の花』と題した吉原細見を刊行開始 | |
| 4話 | 安永4年(1775年)・25歳 | 老舗の版元西村屋与八と共同で礒田湖龍斎の『雛形若菜の初模様』シリーズを刊行 |
| 安永5年(1776年)・26歳 | 山崎屋金兵衛と組んで北尾重政と勝川春章を起用した彩色摺絵本『青楼美人合姿鏡』を刊行 | |
| 安永6年(1777年)・27歳 | 『明月余情』『手ごとの清水』『娼妃地理記』刊行。 | |
| 安永9年(1780年)・30歳 | 朋誠堂喜三二の黄表紙、四方赤良の『虚言八百万八伝』などを刊行。 | |
| 天明元年(1781年)・31歳 | 志水燕十の黄表紙『身貌大通神畧縁記』刊行。作画の北川豊章が歌麿を初めて名乗る | |
| 天明3年(1783年)・33歳 | 日本橋通油町に進出し、耕書堂を開業。狂歌師として「蔦唐丸」を名乗る。喜多川歌麿画の『燈籠番附 青楼夜のにしき』、四方赤良編の『通詩選笑知』刊行。吉原細見の株を独占。『五葉松』を刊行 | |
| 天明4年(1784年)・34歳 | 北尾政演画の『吉原傾城新美人合自筆鏡』、四方赤良編の『通詩選』刊行。 | |
| 天明5年(1785年・35歳) | 山東京伝の黄表紙『江戸生艶気樺焼』、洒落本『息子部屋』、狂歌集『故混馬鹿集』『狂歌百鬼夜狂』『夷歌連中双六』などを刊行。 | |
| 天明6年(1786年)・36歳 | 山東京伝の洒落本『客衆肝照子』、北尾政演画、宿屋飯盛編の狂歌絵本『吾妻曲狂歌文庫』、喜多川歌麿の絵入狂歌本『絵本江戸爵』刊行。 | |
| 天明7年(1787年)・37歳 | 山東京伝の洒落本『通言総籬』、喜多川歌麿の絵入狂歌本『絵本詞の花』、四方赤良編の狂歌集『狂歌才蔵集』、北尾政演画、宿屋飯盛編の狂歌絵本『古今狂歌袋』刊行。 | |
| 天明8年(1788年)・38歳 | 山東京伝の洒落本『傾城觿』、喜多川歌麿の絵入狂歌本『絵本虫撰』刊行 | |
| 寛政元年(1789年)・39歳 | 喜多川歌麿画の『潮干のつと』刊行。恋川春町の黄表紙『鸚鵡返文武二道』刊行 | |
| 寛政2年(1790年)・40歳 | 山東京伝の『小紋雅話』、洒落本『傾城買四十八手』刊行。 | |
| 寛政3年(1791年)・41歳 | 山東京伝の黄表紙『箱入娘面屋人魚』、洒落本『仕懸文庫』『青楼昼之世界錦之裏』『娼妓絹籭』が摘発される。重三郎は身上半減の重過料が課される。 | |
| 寛政4年(1792年)・42歳 | 曲亭馬琴が番頭として蔦屋で働き始める。10月、母の津与が死去。この年より翌年にかけて喜多川歌麿の美人大首絵を多数刊行。戯作制作を断念し、書物問屋として学術関連の書物刊行を始める | |
| 寛政5年(1793年)・43歳 | 結婚を機に曲亭馬琴が退職 | |
| 寛政6年(1794年)・44歳 | この年より翌年にかけて東洲斎写楽の役者絵を多数刊行。十返舎一九が蔦屋に寄宿、黄表紙『心学時計算』刊行。 | |
| 寛政7年(1795年)・45歳 | 版元蔦屋重三郎として確認されている最後の錦絵(東洲斎写楽作)刊行。本居宣長の随筆集『玉勝間』刊行。 | |
| 寛政9年(1797年)・47歳 | 死没 |