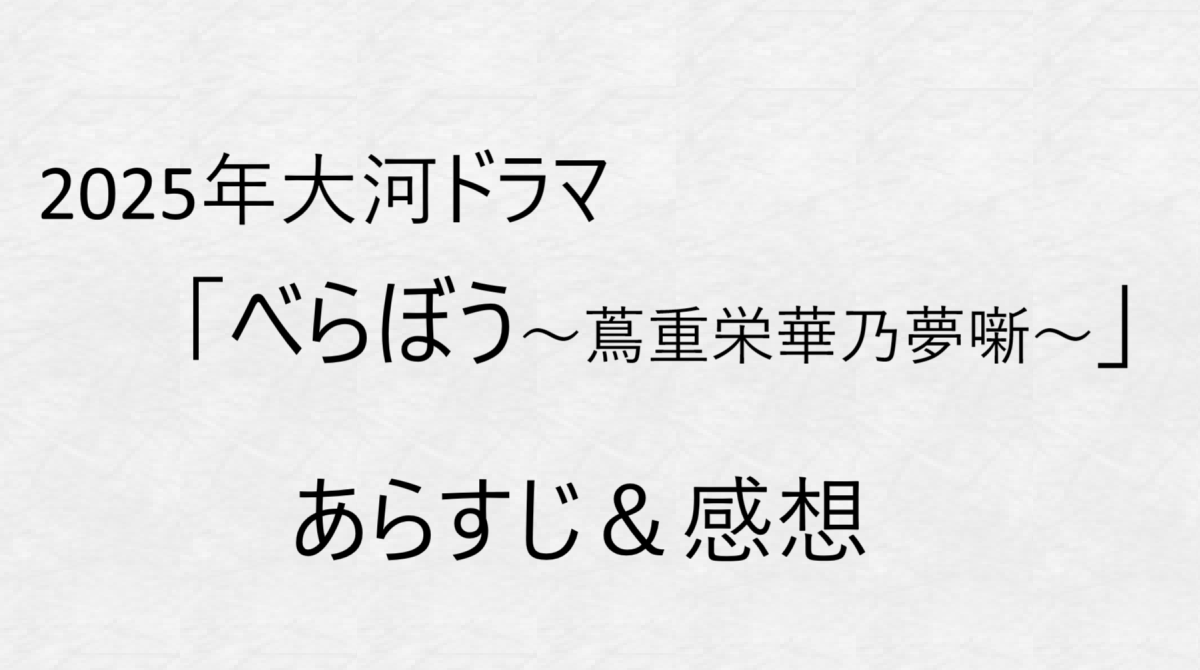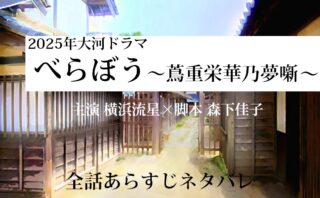横浜流星主演の大河ドラマ【べらぼう】37話「地獄に京伝」が9月28日(日曜)に放送されました。
前回、春町(岡山天音)が自害した。今回、蔦重たちは春町の思いを受け継いで行動しようとするものの…。
本記事は【べらぼう】37話のあらすじネタバレと感想について紹介します!
【べらぼう】37話あらすじ
春町(岡山天音)が自害し、喜三二(尾美としのり)が去り、政演(古川雄大)も執筆を躊躇(ちゅうちょ)する。そのころ、歌麿(染谷将太)は栃木の商人から肉筆画の依頼を受け、その喜びをきよ(藤間爽子)に報告する。
一方、定信(井上祐貴)は棄捐令(きえんれい:幕府が財政難に陥った旗本・御家人を救済するために、債権者である札差に対し債権放棄・債務繰延べをさせた武士救済法令)、中洲の取り壊し(中洲は田沼意次が経済政策として開発した街で、遊郭や茶屋や芝居小屋などがある繁華街)、大奥への倹約を実行する。
中洲がなくなったあおりを受けた吉原は地獄のようになっている。そんな吉原のため、蔦重(横浜流星)は政演、歌麿に新たな仕事を依頼する。倹約が行き過ぎて自分そのものを倹約するというストーリーを提案。
だが、てい(橋本 愛)がその企画に反論し、政演、歌麿に「どうか書かないで下さいませ」と頭を下げる。「市井のいち本屋に過ぎません。お志は分かりますが己を高く見積もりすぎじゃないですか」と、眼鏡をとって強い目つきで説得を試みるてい。
政演は歌麿と2人で話す。歌麿は身を売るしか生きる術しかない人たちにとって倹約の勧めは野垂れ死にすることを意味するという。弱い者につけが回る、という蔦重の意見に賛同している歌麿。
一橋治済(生田斗真)は大奥からのクレームを定信に伝える。質素でも威厳がなくなることはないと考える定信だが、外に出る楽しみもない大奥に理解を示し考えることにする。
定信は、治済から徳川治貞(高橋英樹)が体調不良だと聞いて、会いに行く。治貞は、定信が庶民を締め付けすぎていると思っており、間違えてはいないが急ぎ過ぎては人々が変化についていけないこと、悪をなくなることはないこと、すべては神の御業の賜物なので己の物差しだけで測る危険性などを説く。定信は思い通りにいかないと諫言(かんげん:目上の人に忠告すること)した者に腹を切らせてしまったから、その人の思いに報いたいと答える。
政演、歌麿は蔦重に会いに行く。政演が書いたのは「傾城買四十八手」(けいせいかいしじゅうはって)。蔦重は、みの吉(中川翼)にも読ませる。みの吉は「(女郎の姿に)妹を思い出した。幸せになってほしいと思った」と感想を述べた。蔦重は「女郎を姉妹や知り合いのように思わせる。幸せになってほしいと願わせる。これ以上の指南書はございません」と高く評価して買い取りを願い出た。
政演は馴染みの花魁・菊園(望海風斗)から庶民向けに人の道を教えてくれる本「心学」を知らされる。
一方、ていは「傾城買四十八手」を読み、2番目の話の女郎の客の姿に前の夫の影がよぎったと漏らす。この女郎の幸せを願うてい。蔦重は、定信も読んで同じ思いになってほしいと願った。
定信は将軍補佐として、太上天皇の尊号の一件を不承知とした。一橋治済は不満げだ。大崎が老女の役を免じられたと知る治済。楽しみを減ずることなく倹約したという定信。治済は田沼も真っ青だとあきれる。定信は懸案事項の解決をできる人が他にいるならいつでも退く覚悟だという。
年が明けた。蔦重が作った黄表紙はあまり売れなかった。京伝は人の心の善と悪を擬人化した「心学早染艸」(しんがくはやそめぐさ)を出版。「善玉」「悪玉」という言葉がこの作品から生まれて広まったとされていて、つまり長く読み継がれるほど出来のいい話で、定信が推し進める「倹約・正直・勤勉」をエンタメ化したのものだ。
蔦重は吉原にいる政演に会いに行き、定信をかついでいると批判。政演は「面白ければ良い」と反論。納得しない蔦重は、「蔦重のところで書かない」という政演と喧嘩別れに…。
【べらぼう】37話の感想まとめ
37話ラストでは蔦重が政演と喧嘩別れになってしまいました。
蔦重は世の中を苦しめている定信の政策を変えたい。一方、政演は面白ければ良いという主張。これは相容れないですね。
せっかく蔦重は政演の本を「良い指南書」として買い取ったのに……。まさかこんな展開になるとは。
今後、2人の関係はどうなっていくのでしょうか。また、定信による改革はうまくいのでしょうか。注目していきたいです。
あと、37話で印象的だったのは、おていさんの蔦重への説得。眼鏡を外して「めぢから」をアップして訴えるので見入ってしまいました。凄い迫力でした(笑)