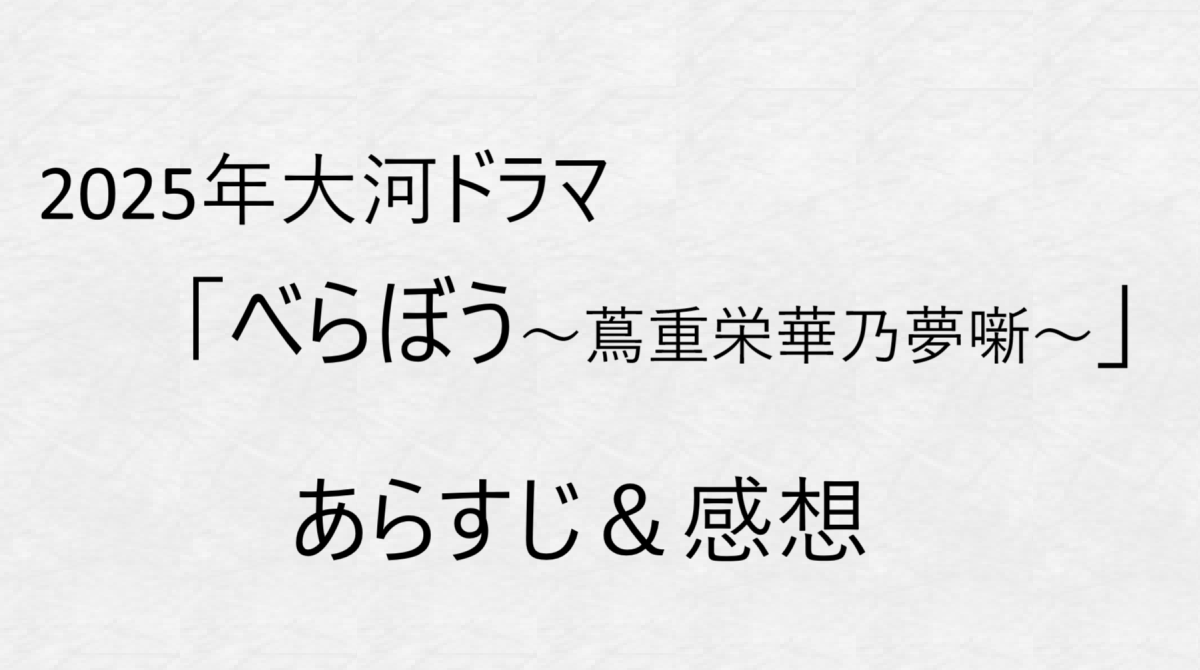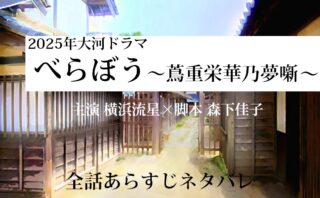横浜流星主演の大河ドラマ【べらぼう】30話「人まね歌麿」が8月10日(日曜)に放送されました。
本記事は【べらぼう】30話のあらすじネタバレと感想について紹介します!
「三つ目!」
— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) August 13, 2025
久しぶりに再会した2人。
ドラマを見返す👇https://t.co/9FCGnfvSEW#大河べらぼう#染谷将太 #片岡鶴太郎 pic.twitter.com/bI2kVqX4oa
【べらぼう】30話あらすじ
天明6年(1786年)、黄表紙の「江戸生艶気樺焼」が売れ、日本橋の耕書堂は開店以来の大盛況となった。一方、小田新之助(井之脇海)とふく(小野花梨)には、長男が誕生。新之助は大泣きする我が子を抱き「お母さんがいいか?」と優しく声をかける。
蔦重(横浜流星)は歌磨(染谷将太)が『人まね歌麿』と噂になっていると知り、かねてよりの計画通り絵師・歌麿の大々的な売り込みに踏み出すことに。蔦重が提案した画題は、枕絵(のちに春画と呼ばれる絵)だ。
蔦重は歌麿に自分ならではの絵を求める。蔦重は「表には流れねえ分、自由。心のまま、我儘に描けるってことだ。どんな女が好みだ? そいつと、どこでどんなことをしてえ? 」 と問う。歌麿は「こういうのは話し合って描くものではない」と独り自室にこもって枕絵の制作に打ち込むことにした。
歌麿は「好きな女……」と思い浮かべる。すると、母(向里祐香)の姿が浮かび、責められる歌麿。さらに、自分たち母子を食い物にした男・ヤス(高木勝也)の姿も現れる。そのふたりの死に関わった歌麿は、描けずに苦しんでいく…。
歌麿は、描き損じを抱えて耕書堂を出た。その描き損じを廃屋の片隅に隠しに行くと…。そこにはうずくまる女がいた。女が顔をあげると、顔を負傷している歌麿の母(※幻覚)だった。女と一緒にいた男を殴りつける歌麿。男をヤスと重ねてしまい、殴ったのか…。
蔦重が歌麿を止める。正気に戻った歌麿。母だと思った見知らぬ女(藤間爽子)は別人だった。
歌麿は「描けねえんだ」「要らねえよな。人まね歌麿で終わる俺なんて」「目いっぱい役に立ちてえとは思ってるんだけどよ……」と蔦重に告げ、泣いた。
その後、鳥山石燕(片岡鶴太郎)が耕書堂に来た。人まね歌麿の筆致を見て、あの時の少年ではないかと思い、訪ねてきたのだ。歌麿は少し遊んだだけなのに覚えていてくれたことに驚く。石燕は「忘れるか、あんなに楽しかったのに。お前は楽しくなかったか?」という。
石燕は「その目にしか見えぬものがあろう。絵師はそれを写すだけでいい。写してやらねばならぬとも言えるがな」「その目にしか見えぬものを現してやるのは、絵師として生まれついた者のつとめじゃ」と歌麿に伝える。
歌麿は「弟子にしてくだせえ。俺の絵が描きてえんです。お傍に置いてくだせえ!」と頼んだ。
石燕の弟子となった歌麿は、耕書堂から出ていくことになった。
歌麿の背を見送る蔦重は「あいつのことを一番わかってるのは、俺だって思ってましたが。素人だったってことですね」と嘆く。母・つよ(高岡早紀)は「あんたには絵を売るって仕事があるじゃないか」 と励ました。
一方、定信(井上祐貴)は、治済(生田斗真)から公儀の政に参画しないかと誘われる。定信は「母の具合が思わしくなく」「今、田安は母が亡くなるまではと、取り潰しの猶予をいただいております」という。定信の母・宝蓮院(花總まり)が当主となっているが、母が亡くなると取り潰しになってしまうということだ。
治済は「たとえ一度取り潰されても、西の丸様の代には必ず蘇らせよう」と伝える。西の丸様とは治済の実子・徳川家斉(長尾翼)のこと。家斉が将軍となったら、田安徳川家を甦らせるということだ。定信は「では政の末席に加わり、田沼を追い落としてみせましょう!」と宣言する。
その後、定信は反田沼派の大名・旗本を固めたり、将軍・家治(眞島秀和)の側室・知保の方(高梨臨)と接触するなど動き出していく。
ラスト。同年7月、大雨が降り、雷鳴が鳴り響く。一橋治済(生田斗真)がびしょ濡れになりながら舞っていた。同じ頃、田沼意次(渡辺謙)のもとに利根川決壊の知らせが入る。治済は天に向かって両手を伸ばし「時が…来た!」と狂気をにじませて笑った。(つづく)
【べらぼう】30話の感想まとめ
鳥山石燕(片岡鶴太郎)の言葉にネット反響
歌麿が枕絵を描こうとして、自分が殺したも同然の亡き母らに苦しめられていく展開に。
そんな歌麿を救ったのは鳥山石燕(片岡鶴太郎)でした。
その目にしか映らぬものを写すだけでいいし、それが絵師の務めである、と…。
シンプルながら、深い言葉だったと思います。
そんな鳥山石燕(片岡鶴太郎)の言葉には多くの反響が寄せられていました↓
#大河べらぼう べらぼう蔦重からは枕絵を描けと指示されたけど、べらぼう石燕からはそのへんのものを描けと言われて、のびのびと庭の花を描き始めるべらぼう歌麿。江戸時代でも良いプロデューサーだけでなく、良い作家仲間、良い師と出会えずに消えていった人、たくさんいたんだろうね。
— カカオ99(カカオ・ツクモ) (@netinago99) August 10, 2025
見えるやつが描かなきゃそれは誰にも見えぬまま消えてしまうじゃろ!
— 🐷子豚のeveちゃん (@little_pig_eve) August 10, 2025
その目にしか見えぬものを表してやるのは絵師に生まれついた者の務めじゃ!
これって絵画に限らず、芸術や創作物全般にも当てはまる気がします。
歌麿にそう諭す鳥山石燕の言葉にとても胸を打たれました。#大河べらぼう#べらぼう
#大河ドラマ #べらぼう
— すえちゃん (@TSueda2) August 10, 2025
どの時代を生きて(演じて)いても時を超越した存在となる #片岡鶴太郎 さん。😲
迷える歌麿に、「その目にしか見えぬものを現してやるのは絵師に生まれついた者のつとめじゃ」と諭す石燕先生。
一連の示唆より、思わず「芸術は爆発だ!」を想起しました。🤔 pic.twitter.com/a5ukYKGkCT
こんやのべらぼう
— ふってん (@Be_Br_happy) August 10, 2025
石燕先生の言葉
すべての🌈創作作家さんへの
クソデカなエールだ
「その目にしか見えぬものを
現してやるのは
絵師に生まれついた者の
つとめじゃ」